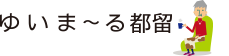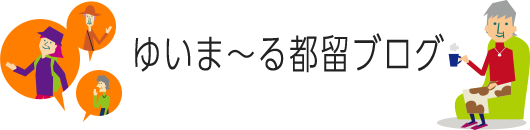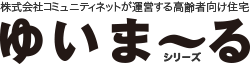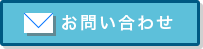居住者が紹介する「都留」の魅力その9 ~お茶壷道中行列~
ゆいま~る都留スタッフ 下田です。
前回ブログでもお伝えしましたが、都留市内で11月10日に行われた「お茶壷道中行列」の様子をお届します。前回同様、ゆいま~る都留の居住者である小田切敏雄さんの写真と文でお送りします。
江戸時代、徳川将軍家御用のお茶を京都・宇治から江戸城に運ぶための「採茶使」一行の行列を「茶壷道中」と呼びました。慶長18(1613)年から慶応3(1867)年まで、約250年余に渡って続いたとされ、その途中一部は甲州谷村(現在の都留市)の勝山城で熟成のために夏の間、「茶壷蔵」に格納されていたと伝わっています。また江戸時代中ごろまでは谷村藩主秋元家に預けるため谷村に立ち寄ることが常とされたと伝わります。「甲斐国志」などによると勝山城の茶壷蔵に格納され、ここで夏を越したともいわれます。

この「茶壷道中」は、子どもの遊びのなかで「鬼」を決める「わらべうた」の「ずいずいずっころばし」に「茶壷におわれてトッピンシャン」と歌われ、「将軍家御用の茶」を運搬するという権威ある「お茶壷道中」は、行列が通る時には沿道の住民は荷物運搬、道普請などの使役といった負担もあったようです。


都留市上谷1の都留市博物館「ミュージアム都留」の前庭には「お茶壷道中の碑」が建てられ、「ずいずいずっころばし」の歌詞とともに富士山を背景にした「お茶壷道中」の様子が絵画で伝えられています。

お茶壷を保管していたとされる勝山城(勝山城跡)は、現在は登山道も整備されており、山頂まで歩いて約30分、お足に自信のある方にはおススメの散歩コースです。都留の歴史にご興味のある方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか!