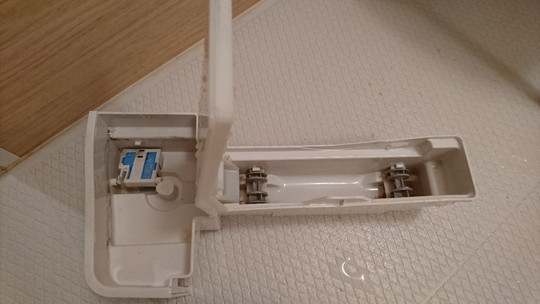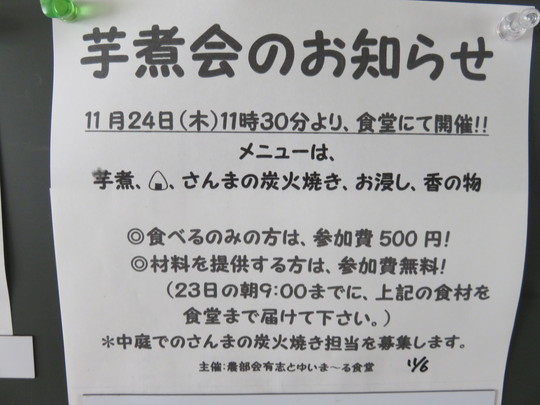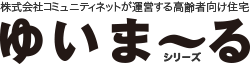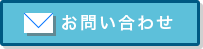人はいくつになっても、どんな状態になっても、誰かの役に立ちたいと思います。
ゆいま~る聖ヶ丘グループハウスには、日常的な見守りや、少しだけお手伝いが必要な方達が暮らされています。介護を必要とされている方達です。
ご病気であったり、認知症であったり、理由は人さまざまです。
先日、ある方のお部屋で私が洗濯物をたたんでいると、ベッドに寝ながら見ていた居住者の方が、こんなことを泣きそうな顔で言われました。
『私はなんにもできない、なんにもできない、なんにもできない』
その方は車椅子生活で左手も麻痺で使えません。ですから、多くの場面で介助を必要とされています。
・・・・・・・・・・・・・
なんとなく違うなと思いました。『なんにもできない』ではなく、
私達が『やってしまっている』から『なんにもできない』と思わせてしまっている。
だから尋ねました。
「一緒にやってみますか?」
『できるかしら?でもやってみたいわ』
その方の表情が変わりました。
一緒に座り、ゆっくりゆっくりタオルをたたみました。
みなさんも右手だけで綺麗にタオルをたたんでみてください。けっこう苦労します。
この方も3枚たたむのに15分かかりました。でも最後に一言
『できたわ!私もできたわ』
と、満面の笑みでした。(おのせできないのが残念)


他にもグループハウスのリビングで掃除機をかけていると、Aさんのじっと見つめる視線を感じました。
「どうしました?」と声をかけると、
『男がやるものかしら』とおっしゃいます。
「手伝ってくれますか」
『なにをすればいいの』
「掃除機をかけていただけますか?」
『いいわよ、かしてごらんなさい』
Aさんの手伝いたい気持ちは満点です。その気持ちを大切にしたいので、何かあった時にはサポートができるよう、つかず離れず見守りをしながら、お願いをしました。
『こんなかんじ?』
「そうですね、いいですね。綺麗になりました。テーブルの下が埃たまっていたので、お願いできますか?」
『了解』

気づけばリビングだけでなく、廊下もやってくださいました。
全部仕事が終わったらリビングで大好きな紅茶を召し上がり、『仕事のあとの一杯はおいしいわね』とおっしゃり、本当にその表情は満足されたようなお顔をされていました。泣き顔も笑顔に変わります。そして満足した顔に変わります。もちろん紅茶のカップも洗っていってくださいました。
『介護』というと、一般的には介護者はやってあげる、してあげる、イメージがあります。でも本当に大切なのは。『まつ』こと。
その方ができないところだけお手伝いすること。スタッフがやってしまうことは簡単です。でもそれは「居住者の生活」としては、ご本人ができることを奪ってしまっています。
人によって求められるサポートはそれぞれです。なかなか難しいこともありますが、居住者の出来ること、やりたいことを一緒にやっていきたいです。