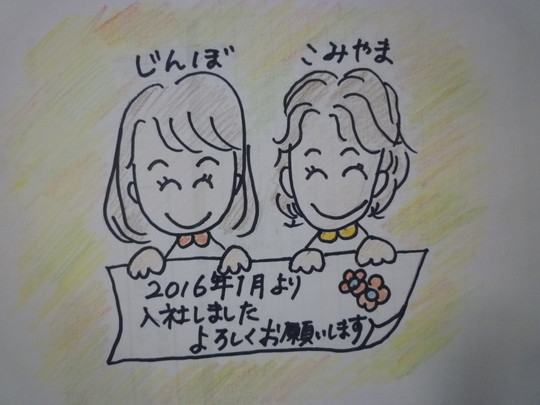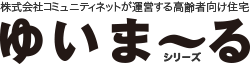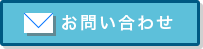2月18日(木)、某新聞社の取材がゆいま~る那須に入りました。
当日の那須町の気温は6度。昨日、雪がちらついたそうで、今朝はとても冷えていましたが、遠くには那須連山がくっきりと見えました。

初代ハウス長より、ゆいま~る那須のなりたち、概要を説明させていただきました。

図書館、音楽室、自由室、モデルームなどをご案内。

ゆいま~る那須は八溝杉を使った木造建築で、どの部屋も窓が大きく取られ、居ながらにして四季折々の季節が感じられます。
入居者Mさんのインタビュー
食堂の一角の「ショップま~る」で、住み替えのきっかけ、今の暮らしぶりをお話しいただきました。

Mさんは「ショップま~る」で衣料品を販売しています。衣類の他、今評判がいいのは、ちょっと小腹がすいた時に購入できるお菓子だそうです。お菓子を通して、入居者の皆さんと会話が弾むのも楽しみの一つだとか。
取材後、ゆいま~る那須の新スポットを歩きました。グリーンプロジェクト部会(居住者5名)の方たちが整備した遊歩道。森の中を危険なく歩けるように、歩くのに邪魔な小枝などは切り、整備されていました。15分ぐらい散歩コースになっていて、森の気配を感じながら、散策が出来ます。

木を切って作ったベンチを発見。とって個性的なベンチでしたが、座り心地がは抜群で、落ち着くいい椅子です。座ると正面に、ゆいま~る那須の食堂が望めます。

ゆいま~る那須へ住み替えされた8割の方は、首都圏からの住み替えをされた方です。冬の寒さも心配の一つですが、ある居住者の方とお話をしたら「一番好きなのは冬だわ」とおっしゃられていました。皆さん、冬の暮らしを色々工夫し、過ごされているようです。
濁りのない冷たい空気が頬をさす感じや、冬の凛とした景色の美しさに、冬は冬の良さを感じました。(広報室)

ゆいま~る那須の前の道。