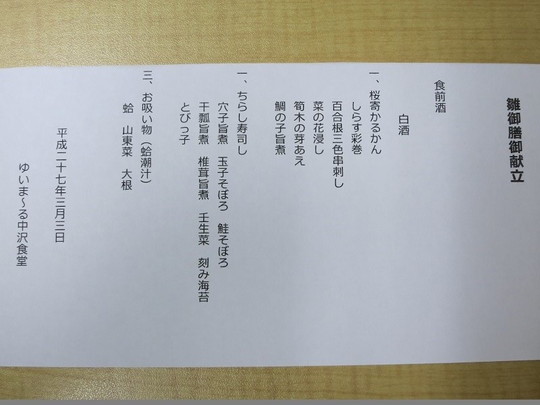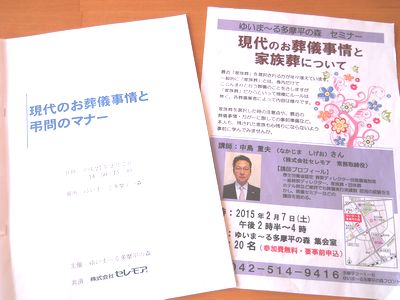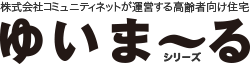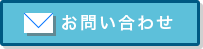1月21日、ゆいま~る食堂が音楽で笑顔いっぱいになりました。
昨年に引き続き、花菜主催で介護職であり、
シンガーソングライターの「堤吉輝さん」のライブコンサートを開催しました。
花菜の利用者とスタッフに加え、ゆいま~るの居住者、
フロントや食堂スタッフ、外部からの参加もあり、来場者は40名近くにもなりました。

花菜利用者のKさんはこの日を楽しみにされており、吉輝さんと半年ぶりの再会に、
少し照れながらも大きな声で「頑張ってくださ~い」とエールを送られ、
「ありがとうございます」の笑顔の返しに会場もなぐっとなごやかになりました。

歌はご自身で作詞作曲された曲、カバ-曲、アンコールで10曲ほどを
ギターやハーモニカで演奏しながら歌ってくださいました。
美空ひばりの「愛燦々」は透き通るような歌声でした。
皆さんの心にも響きわたったことでしょう。
働く施設で出会った「おばあちゃん」をイメージして作られたオリジナル曲
吉輝さんのお人柄を思わせる心温まる歌詞とメロディでした。
歌と歌の合間をつなぐトークも絶妙で、
笑いで緊張をほぐしてくださり、会場はどんどん吉輝ワールドに。

アンコールでは中島みゆきの「糸」をしっとり歌い上げていただきました。
最後の曲「幸せなら手をたたこう」では参加者全員が笑顔でお隣の方と手を繋ぎ合い、
会場はひとつになりました。
普段歌わない花菜利用者のNさんも満面の笑みを浮かべ
「良かった」とそうっと言われ、音楽の力は強いと感じました。


最後に「また会いましょう」「夏に来てください」と言葉を交わし合いました。
今から夏が待ち遠しいです。